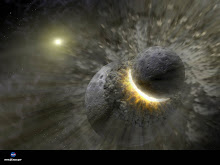ある男が、殺人を犯して死刑判決を受け、処刑されるまでの話。
二部構成になっていて一部は殺人を犯すまで、
二部は刑務所に入り死刑執行までが書かれている。
読みながら、なぜこのタイトルになったのかと考えていた。
一部では、
「自分は世俗には一切関心がないよ」
というスタンスで主人公はいる。
だから君らとは違い、私は異邦人なんだよ、
ということなんかなと思った。
例えばこの本は、「きょう、ママンが死んだ。」
で始まる。しかし母親が死んだことに対して悲しみとかそういった一切の感情は書かれていない。
また、人を殺した状況にしても
そこには、太陽がギラギラと暑かったということだけが描かれているだけである。
ここまでは、村上龍の『限りなく透明に近いブルー』にも雰囲気は似ている。
しかし、二部になってこのタイトルの理由がわかった。
死刑執行までの手順が、すべて「わたし」を除外して進んでいくのである。
殺人の動機は「わたし」の意見抜きで勝手に推測され、
確実に死刑宣告まで進んでいく。
そこに「わたし」の意見は考慮されていないし、
発言権もほとんど与えられていない。
味方である弁護士も諦め、恋人も最後には面会に来なくなる。
司祭だけが、神の加護の下に「わたし」を諭そうとしてやってくるが
そこに神の救いはない。
多数決で人を殺すことを決める際に、
当事者の意思は一切考慮されていない。
この本を読んでいると、
自分にはどうすることも出来ない不条理が確かに存在することを
再確認させられる。
こちらもよろしく↓
次回予告
「ひとりでは
生きられないのも芸のうち」 内田樹